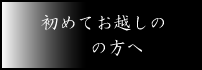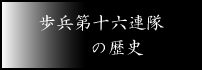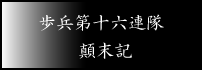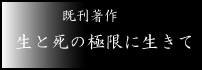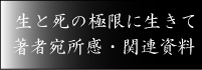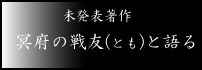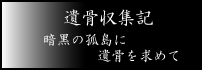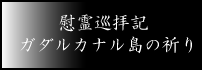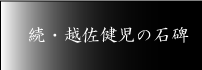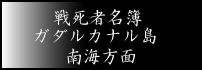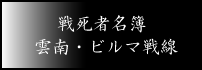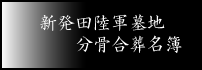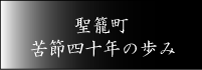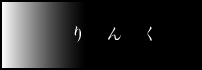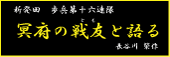日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣
生と死の極限に生きて
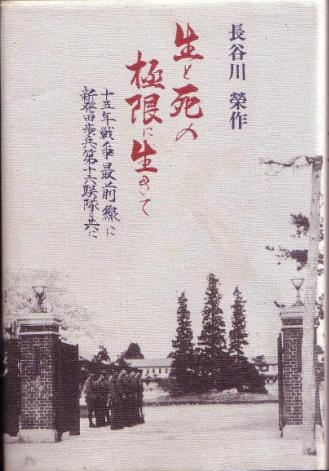
生と死の極限に生きて
十五年戦争最前線に新発田歩兵第16朕隊と共に
長谷川榮作

著者近影
手記を書くにあたり
私はこの手記を書くにあたって次のことを残したいと思って筆をとった。
一、戦死された、戦友の死について納得した確証と意義付けが欲しかった。
二、生と死の極限である戦場にあって若者は何を考え、どのような生き方をしたか。
三、参戦をした立場で戦場の実相について明らかにしておきたい。
四、後日物語的に誤ったり歪められたりしないように戦友の名誉を確保しておきたい。
五、戦争というものがいかに過酷、凄惨なもので愚かなものであるか、空しいものであるかを知って貰いたい。
等であるが素人の悲しさ、意の通じない、足りない、不明や拙文のところはお許し願いたい。
私は昭十二年の徴集兵。仙台第二師団新発田歩兵第十六連隊に入隊、第一期検閲後、満州(以下、地名は当時のものを用いる)に渡る。満州事変の治安維持のための駐屯地任務、支那事変参加(太原攻略まで)、ノモンハン事変参加、昭和十五年十一月新発田衛戌地に帰還、大東亜戦開戦と同時に参戦、常時第十六連隊と共に最前線に従事、昭和二十一年五月十三日復員完結、十六連隊の解隊と共に解職された。この間一貫した戦地戦務ながらも奇跡的に生を得て終戦となり帰還をした。
そして現在七十八歳の齢を得て、当時戦場において支那事変に一回、ビルマ作戦に一回の負傷をして未だ弾片を体内に残して痺れや罹病(湿性助膜炎、虫様突起炎、赤痢、マラリア)による後遺症に加え呼吸器疾患等、満身創痍の身で苦しんでいる。
それ以上に苦しいことは心の傷である。
異郷の地、戦場では連隊将兵六千余名の人たちがひたすら祖国と同胞に想いを寄せて青春の血を流し、散っていった。私が確かめ、納得をし確証を得たいのは、逝くなった戦友の死は何のために、誰のために死なねばならなかったのか、そしてその死の代償は何であったのか、またその死について国民は、国家はどう考えているのか。
我々の青春を奪い、燃え尽くした価値はあったのだろうか。私はその確証が欲しいのである。
我が国も戦後五十年を経て戦争の事実は風化しつつある。それにも拘らず今なお戦争責任を問われ、国の政権が変わる度毎に謝罪外交の行脚をしている。
国民は懺悔をし当時の責任者も命を賭して戦後処理をしたはずである。
国家としても平和憲法に徹し、謙虚に反省をして世界のどこの国よりも平和を愛し、また世界の平和社会に貢献している。
なのに黙って聞いていると侵略だ、略奪だ、虐殺だ等々、戦場における異常行動を暴きたてている。
これがいかにも第一線将兵の全ての如くに聞こえてくる。
このままでは逝き戦友の霊が浮かばれない。生き残った我々も黙っているわけにはゆかない。
あの世に行って合わせる顔がない。
戦友からは何のために生き残ったのかと叱られる。
かといって戦争そのものを正当化しようとは思わないにしても、我々は個人の恣意や私利私欲のために戦場に立ったのではない。
戦争に至るには多くの紆余屈折があり、民族、宗教、領土、経済、思想等の多種多様のことが介在してくる。
しかし、我々は今でも御国の為に戦ったと思っているし確信をしている。絶対に間違いのない事実である。他国を傷つけ侵略するために戦ったとは考えてはいない。
このことを聞いて怒る者は怒ればよいし、笑う者は笑っても構わない。我々の立場を鮮明にしておきたい。
少なくともあの場合、我々が戦場に立たなかったら果たして日本はどうなっていたであろう。
これは誰も解明できないと思う。
大東亜戦争あるいはそれ以前における事変、紛争はなぜ起こったのか。
全貌を詳らかにすることはできないが、ある程度自分が納得確証が欲しいと思う。
こうしたことについては権威ある証拠文献に基づいて詳細に書かれた出版物がある。
私の記したことが正鵠を得ているかどうか、私の独善と浅学の限りであり、当時を想起される諸賢の共感を得ていただければと希っている。
私共の年代は明治維新以後間もない大正、昭和の初期に生まれ、国の定めた方針に従った教育を受け、そして真面目に殉じていったのである。
この間、日本が遭遇したいくつかの国難についての教えが教育の内容であった。
日清戦争、日露戦争、シベリア出兵、第一次世界大戦、満州事変、日本事変(日中戦争へと繋がった)、ノモンハン事変、張瑚峰事変、そして大東亜戦争(第二次世界大戦)へと繋がったことになる。したがって大東亜戦争はなぜ起こったかの原因は遠く遡った過去に芽生えていたことである。
ロシアは帝政時代、既に満州に対する南下政策を進め、日本との調整がとれず日露戦争の要因となった。大東亜戦争の主敵は米国であったが、当時の米国との関係はまだ日本の宿敵ではなかった。
むしろ日露戦争のときは背後地支援をしてくれた友好国であり、そのため勝利の一因となったとも言われている。
しかし、第一次世界大戦において例の加藤高明外務大臣の対支二十一ヵ条の要求問題では欧米の対日反揆を招くに至った。
日本が鎖国をして深い眠りについている頃、既に欧米各国は各種産業の発達によって国力を増強していた。
日本がその鎖国の夢から覚めてみると世界の大勢から遠く離れ、日本の国家体制は極めて未成熟のものであった。
そして昭和八年、日本の満州事変に関する主張に対し、これを侵略行為であると各国が非難し、四面楚歌の中で日本は国際連盟から脱退して国際孤立化に向かって歩き出した。
満州事変はまた中国の排日意識を高め、飛躍的に日中関係を悪化させた。
日本が目を覚ました頃、既に欧米は十八世紀から十九世紀にかけて、米国は米西戦争に勝利して敗者スペインよりフィリピンを領有し、イギリスはビルマを、オランダはインドネシアを、フランスはインドシナをそれぞれ植民地として支配していた日本が近代化のため必要とする東南アジア諸地域の資源は既に欧米諸国に支配管理されていたのである。
日本が大東亜共栄圏を打ち出した時点で時代は遠く去っており日本のアジア進出政策は時代的にも受け入れがたい状況にあったのである。実態はこのような世界情勢において日本の軍部と政治が対外政策に根本的な間違った思い込みをし、時代錯誤があったことは否めない事実である。
満州において、日本が独占的発展を図る意図が明らかになるにつれて、米国は日本を協調関係ではなく、競争相手に切り換えて対日反撥は時と共に強化されていくのである。この辺で日本は、東亜における独占的勢力の拡大政策について反省すべきではなかったか、と識者は説いている。
不幸にもそれができなかった。
しかも米国の国力と国民性に対する認識を欠き、一方にあっては中国の排日運動が本格的なものになり禍根は増幅されていった。
国内にあっては政治と軍事は一体なものでなければならない。
政治が軍事を軽んずると外国の軽侮あるいは侵略を受ける。
逆に軍事が政治を圧迫すると起動を逸して暴走する恐れがある。
こうした政治、軍事の体制も未成熟であり、国際的にも精通し得なかったまたアジア諸国に対しては欧米の圧政から開放して救世主的な歓迎を期待し、日本がアジアの盟主となること不満もなく従いてくるだろうと考えたに違いない。
かくして国際情勢は日に日に悪化するに至った。
しかしアジア諸国は、眠りから覚めて未だ日新しい日本に対して欧米人よりも魅力のある主人とは思っていなかったのではないか。
ところが結果的には日本の敗戦を糧として民族意識に目覚めて植民地から解放されて独立国家として存在するに至り、喜びと活力を生み出すことになったのである。
そして米国は、これら日本の行動に対する外交手段としてついに輸出禁止の措置をとるに至った。
資源の何もない国が出口と入口を塞がれたら、これは国家民族の存亡に関わる大問題である。
この米国と開戦したのは日中戦争が始まってから四年後である。既に日本は経済的にも資源も逼迫した状況にあり、軍事力も全戦力を投じ短期決戦を狙ったものであった。
こんな時代背景に我々は生まれ育ち、多感な少年時代に教育を受け、国家民族の危機の重大さを教えこまれたのである。
ちなみに開戦時における彼我の国力、生産、軍備のことは後述の当時大本営参謀の中枢におられ、最も正確な事態把握されていた智将、井本熊男氏(陸軍大佐)の『作戦日誌で綴る大東亜戦争』の出版書がある。
同書によると、アメリカ一国だけで人口は日本の倍、経済力、資源にあっては十倍総生産力にあっては尺度がない程の圧倒的な優勢を保持する相手であった、とある。それに比べ、我が国の兵器器材の性能といえば、日露戦争当時の三八式歩兵銃を思い浮かべても分かるように幼稚なものであった。
しかし、我々は立ち向かってゆかざるを得なかったのだ。
ここで国際道義からしても、個人の人権を考えても国際史に銘記すべきは、ソ連の許せない参戦である。
ソ連のスターリン首相は、時刻の一方的な恣意と日本の敗戦を見通して、戦後処理に列国と共に発言権を得て漁夫の利を漁るべく米国に申し入れをして、日ソ不可侵条約を踏み躙り連合国に加わって満州に進軍、北方四島はおろか北海道まで狙ったことである。日本はその意図も知らずに終戦直前、スターリンに和戦交渉の仲介を依頼したという事実があったと聞く。
その北方四島問題は未だに解決をせず、しかも終戦直後には六十万人もの在満日本人を連行して過酷な労役を強制し、六万人をシベリアの荒野で殺した。一説によれば日露戦争の報復だとうそぶいていたという。
これこそが戦犯に問われて然るべき国際違反行為として永久に日本民族は忘れてはならない。(この項は私の従軍記以外のことである)
日本も幾度か終戦の時機を模索したらしいが、結局原子爆弾の投下を機として戦運意の如く終戦を決意した。
(一説によれば米国は、ソ連の北海道上陸を阻止する意図をもって終戦を早める手段として原爆投下に踏み切ったとのことである。真相不明)
最高戦争指導者会議ではポツダム宣言受諾の可否について審議が行われ、その結果、三対三と意見が対立し、古代以来初めてという類例のない天皇陛下の決断により受諾、終戦となった。昭和二十年九月二日、ミズリー艦上で日本はマッカーサー元帥に対し、正式に降伏文書に調印した。
我々は当時仏印サイゴンで陛下の放送録音を聞いた。
昭和二十年、軍隊はそれぞれの戦場で、国民は終戦という虚脱の中で身をさらしていた。
戦争で命を落とした人、約二百万人、その傷痕を背負って現在に至っている。
かつての日、歓呼の声に送られて、御国のため死を覚悟で出征した我々が外地から悄然と引きあげて来て、肩身の狭い思いをして生きねばならない不都合には我慢がならない。
国破れて山河あり。我々は戦争によって荒廃した祖国を戦場ですりへった体力をふりしぼって再興のため身を粉にして働いた。その結果、現在の経済発展をはじめ、文化、平和国家を見事に建設した。
しかしながら最近は平和に浸り切って、非常の経験と危機を知らない。豊かさのみを味わって、貧しさを知らない。まことに結構なことではあるが、日本人の心までを失っているような気がしてならない。勿論、新しい文化を構築していくことはよいことであるが、良い文化は継承して貰いたいと希う。
国際情勢に明日の保証はない。しっかりと先行きを見つめて、揺るぎない国家を確立して貰いたい。確かに我が国も一つの時代が過ぎ、新しい仕組みの次の時代に向かって進んでいる。
逝き戦友よ―私の生き長らえた日本および歳月の大筋はこんなものだ。慎んでご報告を申し上げた次第である。
次いで私の実体験と戦友、戦場の実相について身近な限りであるが記してみたい。

新発田原駐地時代の著者

台湾高雄にて 近藤副官(左)と著者