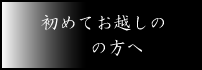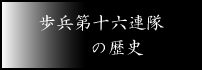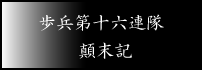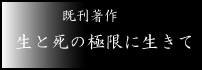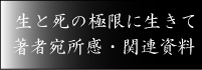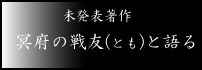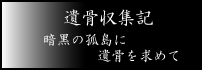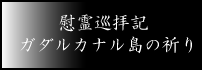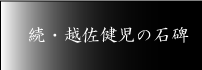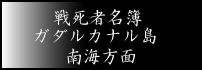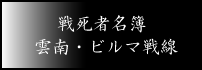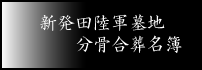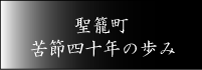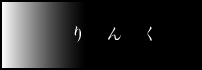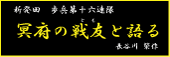日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣
冥府の戦友と語る
敗戦
運命の日、昭和二十年八月十五日、敗戦す。
無条件降伏を受諾す。
サイゴンの師団司令部へ命令受領に集合する。
野田孝次副官に同行する。
命令受領は、ラジオ放送による玉音放送で受聴する。
天皇陛下の録音包装であった。
みんな異常な緊張感に包まれた中で聴いた。
陛下のお言葉は不明瞭でわからなかった。
冒頭前言のところで「朕は万斛の涙を呑んで」のところは陛下の音色でハッキリとわかったが、全体の意味が掴めなかった。
みんなにお励ましの言葉ではなかったかという意見が多かった。
まさか無条件降伏という屈辱的な声明とは受け取れなかった。
しかし停戦宣言的な直感を覚えた。
まさかであった。
まさかはまさかであった。
すぐにも飛び出してどこかへ行きたかった。
みんなショックが大きく身の処し場を失った。
確認を求めた結果はやはり降伏であった。
頭の中が空っぽになって何も手がつかなかった。
しかし事態の進行は早かった。
動きは我々の兵舎に並列していた佛軍の兵舎から始まった。
立場が逆転したことになる。
昨年クリスマスの食用として飼っていた我々の七面鳥が垣を越えて仏軍弊社に行ってしまったが敢えて事を構えて取り返しもしなかった。
しかし何のトラブルもなく、そのまま彼等のものとなった。
立場は逆になった。
我々はとにかくも、祖国日本の国土は国民はどうなるのであろうか。
母國の今後のことだけが気になって落ち着かない。
東南アジアの国々(タイを除く)フィリッピンは米国、インドネシアはオランダ、佛印はフランス、マライ・ビルマはイギリスと殆ど異民族に支配され二十世紀に及ぶ長い間苦しみ悲しみの期間であった。
我々は、その実態を目にし肌で感じて来た。
我が国の将来無条件降伏のもとでどのような運命が訪れるのか、生殺与奪の権をにぎられているのだ。
むしろ戦争より酷な将来が待っている。
さあどうする。
こんなことが頭をよぎる。
相手がどう出るのか、こんな想いを籠めて悶々の日々が続く。
この地ベトナムでもこの戦争に刺激されてフランスの支配植民地より脱却独立主権の奪回が提起され大きなうねりが起きている。
一方敗戦による最初の措置として我々の武装解除がある。
しかし幸いに今次大戦の主戦国である英軍がこれに当たることとなった。
これが我々に幸いした。
勿論ビルマで正面の敵も英軍であった。
流石英国は紳士、騎士道の国家である。
英国騎士道に則り武装解除といわず、ツドモウ近くの丘に集合を指示して、帯刀本分者に対して献刀式という儀礼をもって遇した。
堺連隊長以下我々は刀を捧げ英印軍の殊勲者である軍曹に渡した。
他の戦闘地域には例のなかった式典であった。
英印軍第二十四師団長師令官、マウトバッテン伯爵と日本軍南方方面総司令官、寺田壽一閣下はお互いに寺内閣下が英国大使館付武官の時代からの知己であったとのことである。
従って佛印は佛軍に代わって英軍が管轄をして我々の抑留中の扱いも大変心配りが厚かった。
食糧は特に豊富に補給された。
尚英軍が佛軍に代わって管轄したことについては次の事件が要因であった。
激戦に伴って佛印サイゴンには多くの一般人邦人が集結した。
その邦人がフランス軍から非道の扱いをされていると日本の軍部に泣訴があった。
それを受けた総司令部から師団司令部に伝わり、我が軍としては敗戦の痛手に迷い込んでいるとき、たとえ武装が解除されたとしても佛軍が相手であれば竹槍でも一戦を辞さないと準備にかかった。
前記のように敗戦により命の捨て場など語り合っていたときでもあるり、一般邦人を見捨てることは出来ないということになった。
そのことを英軍に話し通したところ、わかってくれて、英軍がそれに代わって管轄するからと懇篤に慰撫され我が軍も承諾、事件は治まった。
その後、休日本軍は武器がなくとも油断がならないという定説になった。
過去における戦歴をみても武装というには程遠い日本軍の姿を考えればそのように定説を生み出すだろう。
柔道もフランス軍に恐威を与えた。
現地で我々は自活に等しい抑留生活を送り、現地で定着帰化したい希望もあった。
我々は現地で主食以外の野菜類は自給自足をした。
土壌が肥沃で農作物はよく稔った。
栽培方法も品種も現地の人達と違って現地の人達は大変驚く程のものだった。
農業経験のある私はこの地で農業経営をして居残りたいと思って連隊長に相談をした。
この地ではフランス人の身元引受人があれば残れるということであった。
農地を手に入れて農業経営をやることに自信をもった。
サツマイモ・トマト・茄子・胡瓜・野菜が大変よく出来て現地人から熱心に教えを頼まれた。
広大な土地も入手出来る見とおしもあった。
しかし問題があった。
ホーチミン氏を首班とする独立軍が立ち上がった。
もともと日本と親交のあった国でもあった。
日本の敗戦を機にホーチミン軍は我々に独立軍に参加指導教育をして貰いたいとのことで熱心な誘いがあった。
定着移民どころではない。
勿論政府レベルの事でもない、夜になるとひそかに我々のところにしのび寄るように誘いに来る。
眞剣な頼みであった。
待遇や家屋、配偶者のことも含めて軍の指導者、構成員になって貰いたいとの勧誘に来る。
この国の独立確保のために国民的な総力決戦になっているのだ。
我々は祖国の現状もわからず、噂によればソヴェトが我が国に侵攻して来て大変な状況になっているとか。
国へ帰すと船は出すがフィリッピンの沖にゆくと沈める等の噂が飛んでいる。
この際ここに残って自分の人生をかけようと考える人達も数多くなった。
好条件で誘いに来るホーチミン軍に行く者が出て来た。
離隊してゆく人々を拒むことは出来ない。
家庭事情のある人もおり、青春の血潮が騒ぐ者もいる。
静かに見守った。
離隊して行った人達が夜ひそかに訪ねて来て衣類や日用品を貰いに来る。
愈々我々の帰国が決まったとき、私が隊を出てホーチミン軍基地であるクラッチェまで出向いて帰国の決定を伝え一緒に帰ろうと云ったが二人のみ戻った。
既に一家を構えていた「人情に国境なし」「人間到るところ青山あり」人間の順応性と同化力には感じいった。
幸多かれと祈り別れた。
祖国日本が平和な時代、大正初期から昭和初期にかけて社会経済が未成熟で若者の希望が叶えられない日本の青年達の多くは海外雄飛に夢をかけ、それぞれに自分の人生を選んだ若者が多かった。
私もこの場合本部事務の責任がなければここで残る道を選んだかもしれない。
この結末は後刻判明した。
選んだ道は独立戦争という険しい混乱した状況の中で希望通りの人生の道は生き抜けなかった。
福島県棚倉町出身の小林満君は離隊者であった。
帰国後、母親から私に福島から何回か電話があり、わたしは八十一歳の高齢でもあり生きているうちに「満」の墓を建ててやりたいので死亡の手続きをしてほしいとのことであった。
満君はこんなによいお母さんがいたのに、なぜ帰らなかったのかと思った。
私が厚生省に出向いて事情を説明して、私が死亡確認者になって戦死の手続きをとった。
離隊してホーチミン軍に行った人達は全員佛軍の密告懸賞金手段によって処刑されたとのことである。
連隊は昭和二十一年五月三日復員完結したが、離隊した最後の小林満君は昭和三十三年戦死として手続きを終えた。
降伏受諾、帰国復員完結の昭和二十一年五月三日まで約九ヶ月は我々の人生は無籍者の如く長い空白と不安焦燥の日々であった。
この待機中英軍は格別な拘束や圧力もなく我々の自主性を尊重してくれた。
戦勝国として雅量の大きさは国際的にも人間としても尊敬をし将来とも学ぶべきところであった。
サンジャクに原野を整地して葦屋を建てた。
兵の中には大工もおり連隊長の家屋などは置いてくるのに勿体なかった程立派なものであった。
ソヴェトの非人道的な扱いは憎んでも足りない、なぜ国際問題としなかったのだろう。
これも無条件降伏のつけか、しかしソヴェトに戦闘をしかけたわけでもなかったに、居直り強盗ではなかったのか。
今後の国際関係での友を選ぶべき大きな示唆となったのではないか。
この待機中に戦傷病没者の事務や帰国者の関係書類をはじめ、戦闘詳報、陣中日誌、戦時名簿、現認証明書、事実証明書等故国での身分証明確保に必要な事務を完全に処理をすることが出来た。
残念ながらこれら書類は五月十一日大竹港入港と同時に待ち構えていた進駐軍によって全部封印の上押収された。
こんなことになるのなら佛印において九ヶ月間、我々の生殺与奪の権を持っていながら国際条約以上に寛大に扱ってくれた英軍に渡せばよかったと思った。
武器でもないのに彼等は歴史の資料化今後の戦略資料とするのか、残念であった。
英軍は我々日本軍の勇戦に対し賛辞さえも贈って惜しまなかった。
敗戦の傷は英国の騎士道によって癒された。
逝き戦友にも届けたかった。
愈々我々の帰還が決まった。ホーチミン軍に加わった人達が戻ることを待ったが遂に誰も戻らなかった。
立派な決意、生き方でもあると云いたい。
我々は佛印サンジャック港からアメリカの準備したという輸送船によって帰国をすることになった。
乗船は一列に並びゆっくりと歩かされた。
首実験のためにである。
両側には予め手順を整えてあった。
戦場における、犯罪行為の被害者が首実検の為並んで待っていた。
あの場合間違いでも、指をさされたら否定をしても駄目であろう。
この間違えての指名が心配であった。
しかし十六連隊の戦場には犯罪行為に結びつくものは無いと自信を持っていた。
幸い該当者はいなかった。
出港さして船がフィリッピン沖に来たとき、工兵隊の人と聞いたが、マストの梯を登って中断のところから玲瓏とした尺八の音を流した。
粛として声なく晴れた夜空に星が輝いて、波が静けさの中で船べりを叩く音も流れた。
まさに厳かな逝き戦友との決別譜にふさわしい葬送曲でもあった。
その曲は江差追分であった
。
南国の戦場よ、戦友よさらば、我が運命の糸はどこに流れ、どこに結ばれるのか、悲しみと不安が交錯して船は進む。